<吉野川水系> ▲
~吉野川~
長沢ダム[便覧]
[wiki]
河川 吉野川水系吉野川
目的/型式
P/重力式コンクリート
堤高/堤頂長/堤体積
71.5m/216.6m/235千m3
流域面積/湛水面積
91km2 ( 直接:70km2 間接:21km2 [大森川ダム(→大森川発電所)]) /140ha
総貯水容量/有効貯水容量
3,190.0万m3/2,843.0万m3
ダム事業者
四国電力(株)[立案:四国中央電力(株)・完成:日本発送電(株)]
着手/竣工
1941/1949
四国電力(株) 長沢発電所[水力]
所在地:高知県吾川郡いの町長沢
運開:1949.4[日本発送電(株)]
ダム式・貯水池式
認可最大出力:5,200kW 常時出力:2,300kW
最大使用水量:9.50m3/s
有効落差:64.94m
水車:立軸フランシス水車 出力5410kW×1台
流域面積:91.5km2
取水:吉野川[長沢ダム]663.7m
放水:吉野川598.0m
分水第一発電所吉野川取水堰 ▲
取水位:EL586m→
地図上の値。実際は592m程度はありそう。
取水量:
~大森川~
大森川ダム[便覧]
河川
吉野川水系大森川
目的/型式
P/中空重力式コンクリート
堤高/堤頂長/堤体積
73.2m/191m/146千m3
流域面積/湛水面積
21.5km2
( 全て直接流域
) /92ha
総貯水容量/有効貯水容量
19120千m3/17320千m3
ダム事業者
四国電力(株)
着手/竣工
1957/1959
四国電力(株) 大森川発電所[水力]
高知県吾川郡いの町長沢
運開:1959.8
ダム水路式・混合揚水式
最大出力:12,200kW
常時出力: 0kW
最大使用水量:12.00m3/s
有効落差:118.00m
水車:立軸フランシスポンプ水車 出力
12600kW×1台
導水路:圧力トンネル延長2472.6m
流域面積:21.5km2
上部貯水池:大森川[大森川ダム]780.00m
下部貯水池:吉野川[長沢ダム]652.86m
分水第一発電所大森川取水堰[DB]
▲
取水位:EL593m
取水量:
(主要取水設備) 高さ (m) 9.50
(主要取水設備) 堤頂長 (m)
48.76
|
大橋ダム
早明浦ダム
→吉野川篇へ
|
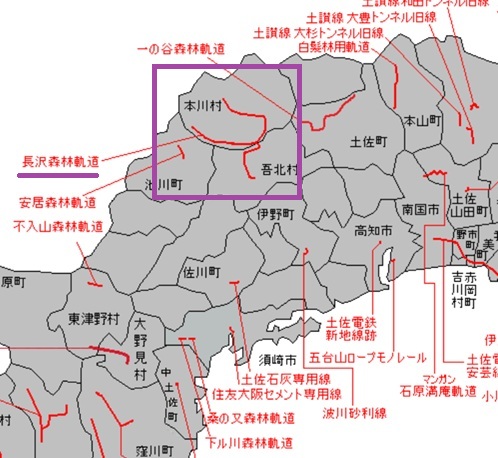 出典:四国の廃なものと鉄道
出典:四国の廃なものと鉄道



 出典:国
交省
出典:国
交省