
発電所一覧(①~⑯の情報は2018年 12 月 現在)
| No |
発電所名 | 事業者 | 利用河川等 | 出力(kW) |
水量 (m3/s) |
落差 (m) |
備考 | |
| 最大 |
常時(対最大常時比) |
|||||||
| ① |
大棚(おおだな) | 東京発電(株) |
芝川 五斗目木川(ごとめきがわ) |
630kW |
450kW(71.4%) |
5.00m3/s |
15.65m |
既設小水力 |
| [1] |
猪之頭 |
〃 |
芝川 |
4,000kW |
2,200kW(55%) |
10.00m3/s |
50.13m |
|
| [2] |
足形 |
〃 |
芝川 |
1,900kW |
1,500kW(78.9%) |
7.43m3/s |
30.91m |
放水:内野発電所 |
| [3] |
内野 |
〃 |
足形PS |
1,700kW |
1,400kW(82.4%) |
〃 |
29.10m |
|
| ② |
白糸 | 〃 |
芝川 | 650kW |
225kW |
4.17m3/s |
24.24m |
既設小水力・放水:猪の窪川(芝川合流部) |
| [4] |
狩宿(かりやど) | 〃 |
芝川(白糸[24.12訪]・音止) | 1,700kW |
1,700kW(100%) |
4.16m3/s |
50.0m |
常時=最大→水量増やせる筈 |
| ③ |
半野(はんの)[24.12訪] | 〃 |
(横手沢?→)半野川[24.12訪] | 200kW |
34kW(17%) |
0.83m3/s |
34.50m |
既設小水力 |
| ④ |
熊久保 | 王子エフテック(株) |
〃 /原川(はらかわ) | 420kW |
1.113m3/s |
〃 放水:大堰用水(大堰川) |
||
| 小水力発電設備 | 白糸滝養魚場 |
湧水(半野川) |
19.8kW |
約3.5m |
https://rief-jp.org/ct10/105353 |
|||
| [5] |
大倉川 |
東京発電(株) |
大倉川 |
1、900kW |
1,500kW(78.9%) |
2.37m3/s |
100.15m |
|
| ⑤ |
観音橋 | 〃 |
芝川 |
970kW |
150kW(15.5%) |
1.67m3/s |
72.03m |
既設小水力 |
| [6] |
東原 |
王子エフテック(株) |
〃 |
965kW |
4.035m3/s |
〃 →ただし『ふじのみや探検第28号』で
は 何故か小水力にカウントされず |
||
| ⑦ |
的場第二 |
〃 |
大堰(おおぜき)川 | 270kW |
3.06m3/s |
既設小水力 | ||
| ⑥ |
的場第一 |
〃 |
〃 |
250kW |
1.948m3/s |
〃 |
||
| ⑧ |
猫沢(ねこさわ) [24.12訪] | 東京発電(株) |
猫沢(ねこざわ)川 [24.12訪] | 400kW |
1.66m3/s |
33.35m |
〃 ・ねこ「さ」わPSにねこ「ざ」わ川なのか? |
|
| [7] |
北原 [24.12訪] | 〃 |
芝川・猫沢PS [24.12訪] | 1,100kW |
740kW |
5.56m3/s |
25.77m |
|
| ⑨ |
青木[24.12訪] | 〃 |
大堰(おおぜき)川[24.12訪] | 840kW |
840kW(100%) | 1.39m3/s |
75.90m |
既設小水力 |
| ⑩ |
大鹿窪(おおしかくぼ) |
〃 |
芝川 |
770kW |
560kW(72.7%) |
5.57m3/s |
16.87m |
既設小水力 |
| [8] |
鳥並 |
中部電力(株) |
芝川 |
1,200kW |
950kW(79.2%) |
8.348m3/s |
16.88m |
放水:西山PS |
| [9] |
西山 |
〃 |
鳥並PS |
2,100kW |
1,600kW(76.2%) |
8.125m3/s |
30.22m |
放水:長貫PS/芝川 |
| [10] |
長貫 |
〃 |
芝川・西山PS |
3,400kW |
1,600kW(47.1%) |
〃 |
50.55m |
|
| [11] |
芝川 |
王子エフテック(株) |
芝川、久保川、小久保川 |
1,500kW |
965kW(64.3%) |
4.17m3/s |
47.09m |
|
| ⑫ |
芝富 | 中部電力(株) |
芝川,長貫PS? | 630kW |
520kW(82.5%) |
11.408m3/s |
7.43m |
既設小水力 |
| ⑪ |
富士宮マイクロ 水力発電設備 |
王子マテリア(株) 富士工場? |
湧水 | 既設小水力・https: //www.jstage.jst.go.jp? | ||||
| [※] |
? |
|||||||
| [12] |
潤井川第一[24.12訪問] | 王子エフテック(株) | 潤井川[24.12訪問] | 1,360kW |
890kW(65.4%) |
4.90m3/s |
34.85m |
中水力 |
| [13] |
〃 第二[24.12訪問] | 〃 |
〃[24.12訪問] | 4,200kW |
2410kW(57.4%) |
10.52m3/s |
50.0m |
〃 |
| [14] |
〃 第三[24.12訪問] | 〃 |
〃 ・潤井川第二PS[24.12訪問] | 2,600kW |
1,970kW(75.8%) |
11.13m3/s |
31.32m |
〃 |
| ⑯ |
本門寺第一(内野) |
三峰川電力(株) |
北山用水 |
120kW |
新設小水力・三峰川電力 |
|||
| ⑮ |
本門寺第二(上井出) |
〃 |
〃 |
140kW |
〃 ・ 〃 | |||
| ⑭ |
しずぎんアクアエナジーパーク 家康公用水発電所 |
東京発電(株) |
〃 |
158kW |
23.8m |
〃・約11.0GWh/年 19運開・21.10リニューアル・NHK・TBS・静銀 |
||
| ⑬ |
富士山本門寺堀発電所 |
(N法)富士山スマート エナジー |
〃 |
9.9kW |
0.4m3/s |
4.75m |
〃 N法:NPO法人 |
|

 24.12
24.12


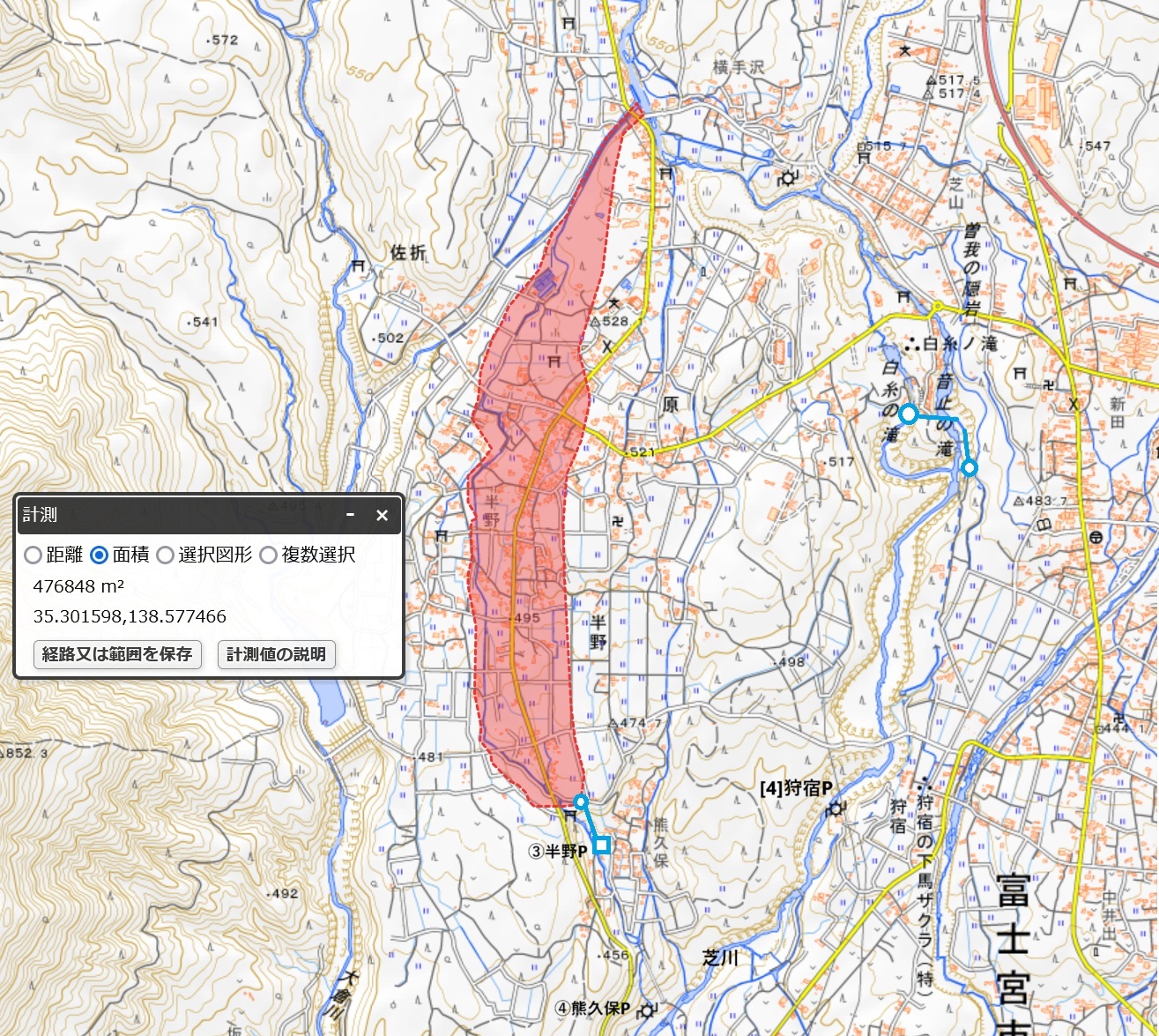

 24.12
24.12 





 出典:
出典:









