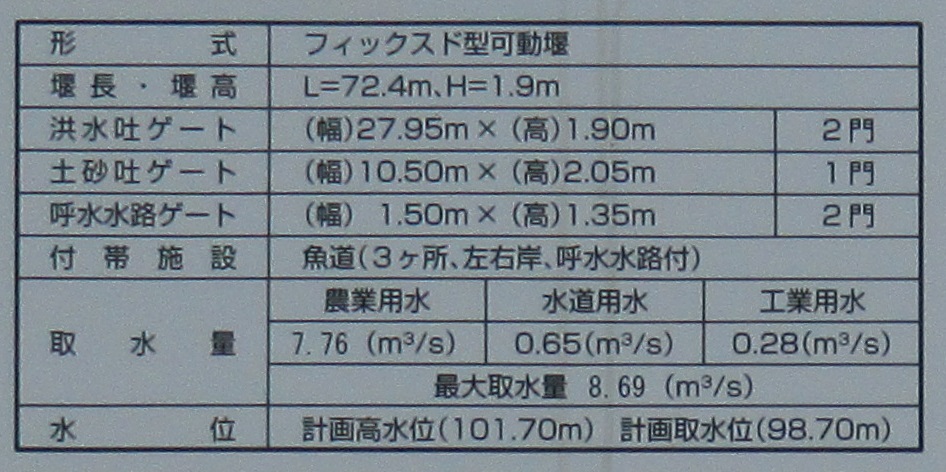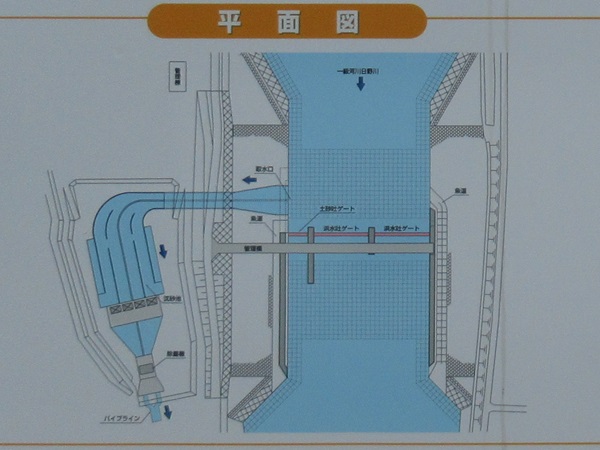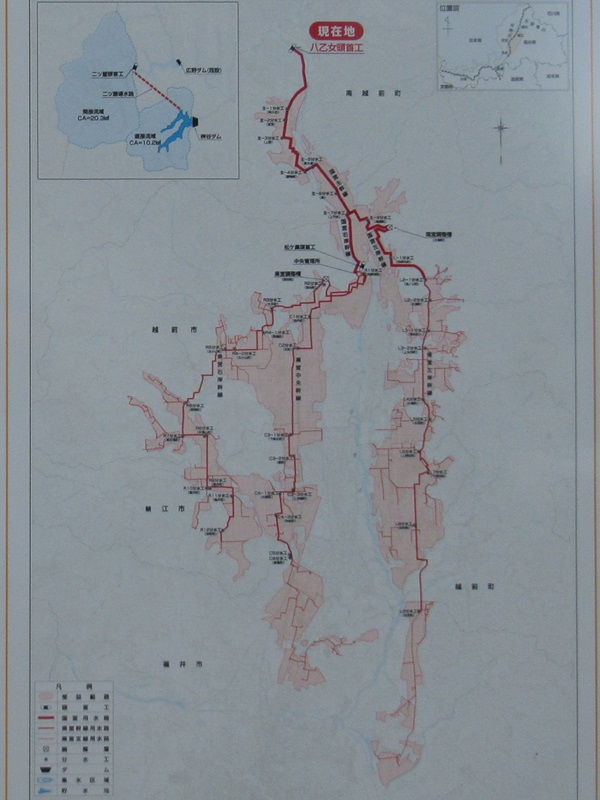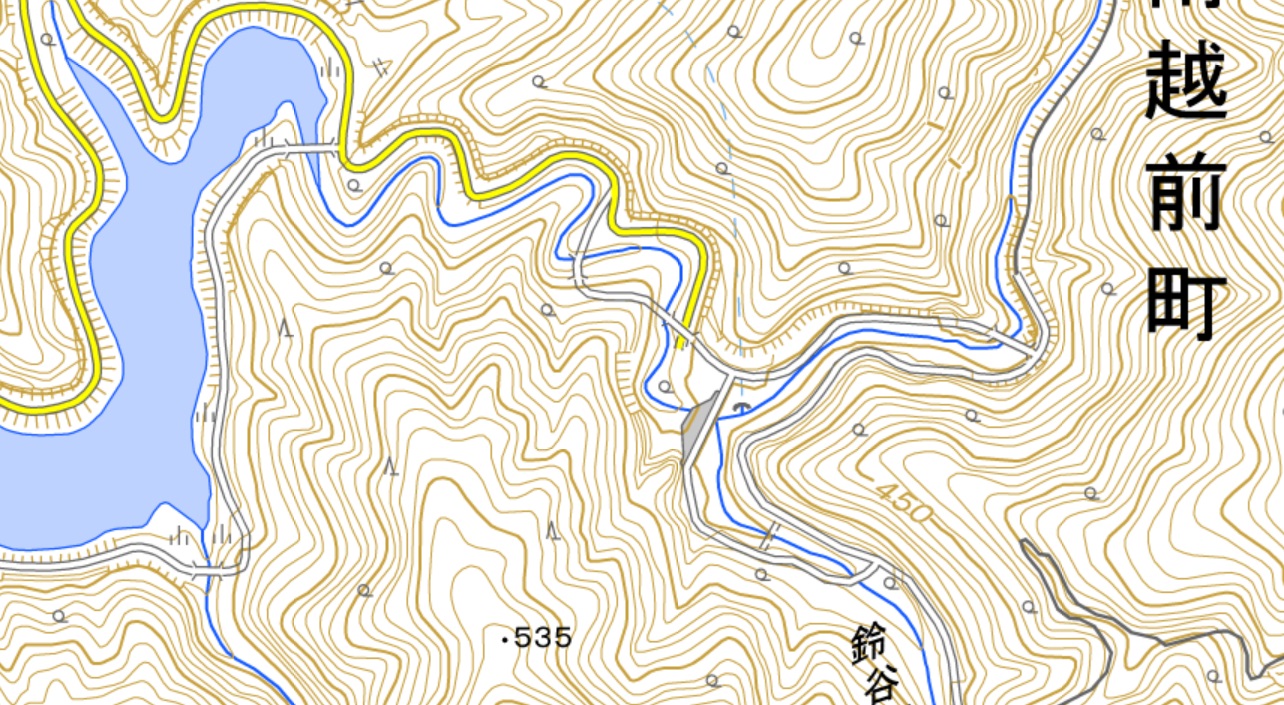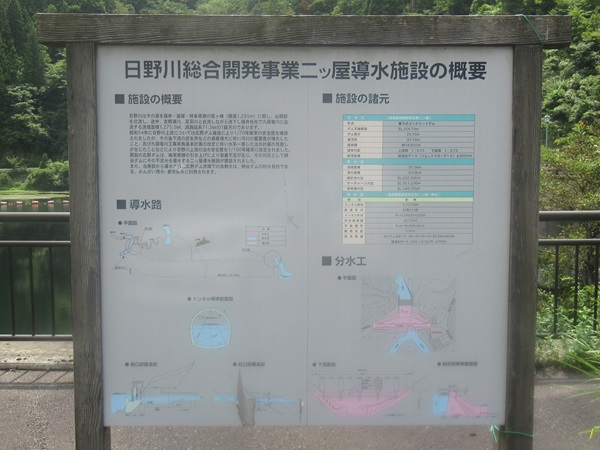�`���J��`�@�@�@�@�@��
�b���オ��ƃ��b�N�t�B���_���������Ă���B

���ɂ͔��d���炵���������B���D�s���ŐS�z���ꂽ�������^�J�ɂ����������l���B
���J�_���m�֗��n�m��
�䌧�n
�ړI�F FAWI
�獂�^�璸���F 100.4m�^345.9m
�_���V�[�W���^�_����b�W���F
����ʐρ^�X���ʐρF 30.5km2 �i ���ځF10.2km2 �ԐځF20.3km2 �j �^89ha
�������e�ʁ^�L�������e�� 2,500.0��m3�^2�C310.0��m3
���펞�ō������ʁFEL.334.4m
�_�����Ǝ� �k���_����
����^�v�H 1979�^2005
�L��_���㗬����
�����Ĉ������Ă���B
���Ă��̖��J�_���ł��邪�C�����͔��d���v�悳�ꂽ�悤�ł���B
2013�N5��27�����j��
���݂Q�_�� �����͔��d
http://j-water.blogspot.com/2013/05/blog-post_4649.html
�ǔ��V���A2013/05/26
�@��z�O���Ə��R�s�ɂ���Q�����̌��c�_���ŁA���������͔��d������v���i�߂Ă���B�_���̌���ɔ��d�ݔ��𐘂��t���鎖�Ƃ͌����ł͏��߂ĂŁA
�Q�O�P�U�N�t�̉ғ���ڎw���B����A���h�_���ł����l�̌v���n���s���Ȃǂ������������A�̎Z���ɖ�肪����A���������������ł���B�i��{�F�I�q�j
�@�V�������錧�c�_���̂����A�u������v�i���s�{�ˁj�A�u�L��v�i��z�O���L��j�A�u�����@�v�i���s�ۉ�����|�c�j�̂R�����́A���ݎ����甭�d�@���
���Ă���B��N�V���A�Đ��\�G�l���M�[�Ŕ��d���ꂽ�d�C���Œ艿�i�Ŕ�����鐧�x���������ꂽ���߁A���́u���J�v�i��z�O���F�Ô��j��
�u��y����v�i��
�R�s���R�j�ɂ����d�@�\���������邱�Ƃ����߂��B
�@���J�_���͗�������W�Q���[�g���ŁA�P�b������X�`�O�E�P����
���[�g���̐������������B���̐��͂��g���A�R�S�P�L���E���b�g�̏o�͂̔��d�@���
�u����v���ŁA�N�Ԃ̔��d�ʂ͈�ʉƒ��S�O�O���ѕ��̂P�T�P��
�S�O�O�O�L���E���b�g���ɂ̂ڂ�E�E�E
(���P)���J�_�������͔��d�{�ݐ����H�� ����2
(2015�N01��23������)
https://www.njss.info/offers/view/5882784/
2015/11/29
���䌧�����̌��z�H���A�ƎҌh���@���D���ʂ̂R�����s���A�s���y����V���z
http://j-water.org/tag/%E7%A6%8F%E4%BA%95%E7%9C%8C/
�i2015�N11��29���ߌ�5��00���j
�@���䌧���{�N�x�㔼���ɓ��D���ʂ��m�F�������z�H���̂����A�P��ŗ��D�҂����܂�Ȃ��u�s���v�Ɓu�s���v�̊������R�O���ɏ���Ă������Ƃ��A�������H��
���D�Ď��ψ���Ŗ��炩�ɂȂ����B�O�N�����̂X������啝�ɏ㏸�B���Ԃ̌��z���v�������Ȉ���A���i�ʂŕs���Ȍ����H�����h������Ă�����Ԃ����������
�Ȃ��Ă���B
�@���̎����ɂ��ƁA���z�H�������͂T�O���ŁA�������D�҂��Ȃ������u�s���v�͂P�P���A���D�҂͂����������ʂŐ܂荇��Ȃ������u�s���v���S���������B�O
�N�����͍H���S�R�����A�s���S���݂̂������B�y�؍H���Ȃǂ��܂߂��S�̂ł́A�{�N�x�㔼���̕s���A�s�����͂U���ŁA�O�N�������Q�|�C���g���B���z�H����
�s���A�s�����ˏo���錋�ʂƂȂ����B
�@���ʂ̕s���A�s�������ł݂�ƁA�W�����P�O�����T���A�X���͂X�����W���Ɩڗ����A�։�s���̃��j�^�����O�|�X�g���đւ���A���c�Z��̑ϐk�⋭�A���J�_���i��z�O���j�̏����͔��d�ݒu�Ȃǂ��������B�����
�Z��i�z�O���j�̕����A�����R�������i��܂��Ƃ���������j�Ƃ��������̖ڋʎ��Ƃł��_��ł��Ȃ����ԂɊׂ����B
�@���͋Ǝ҂ւ̕������̌��ʁA�u���i�����ɍ���Ȃ��v�u�S�H�����肢���ς��ŁA���ޒ��B���s�\�v�Ƃ̗��R���������Ɛ����B�ď�ɖ��Ԃ̍H�����W������
���Ƃ��e�������Ƃ����B������ύX���čē��D���A����ł͂����ނ˗��D�Ɏ����Ă���Ƃ����B
�@�܂����D���́A�{�N�x�㔼���̌����H���S�̂̕��ςX�Q�E�X���ɑ��A���z�H���͂X�U�E�T���B�Ǝ҂̓w�͂ɂ��l�����̗]�n�����̍H���Ɣ�ׂď��Ȃ�����
��������B |
���̌㊮�������Ƃ����b���͕����Ȃ��̂Ōv�悪����Ă��܂��ĂȂ����S�z�ł���B�B
���䌧�@���J���d��
���D�F�Q�O�P�T�c�s��
�_�����E�����r���H
�o�́F340kW
�ő�g�p���ʁF0.5m3/s���x�H
�L�������F82m���x�H
�搅�F���J��m���J�_���n
�����F���J��
���̌�C���J�_�����d�����L�ڂ��ꂽ�������C�����͂����悤�ł���B
��c�������{�ݓf����(�����H)[�������{��]
�w�ǎ搅���ĂȂ��l�q�������B �L��_���̓����͌��\���ʖL�x�Ŗ��J�_���͌��\���ʒႩ�����̂ɂǂ������^�p���H�H

����]�H�̉��̕��ɂ������B
 
|

 �o�T�F���䌧
�o�T�F���䌧 �o�T�F�k
���_����
�o�T�F�k
���_����