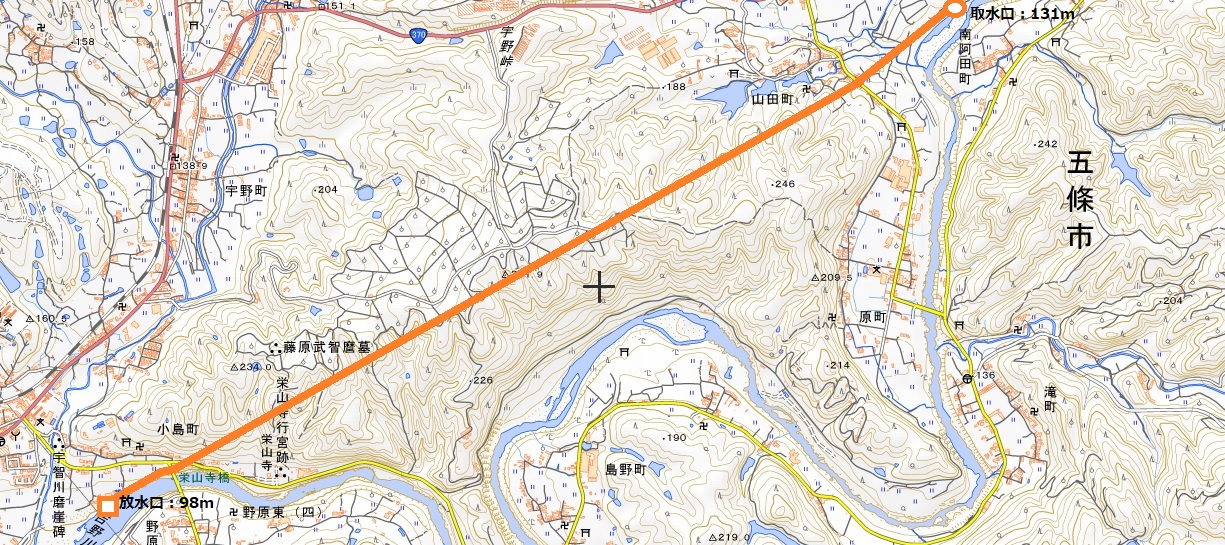津風呂湖の水は発電には未利用の様である。高 見川(238.4m)(東吉野村131.65km2の大部分123.4km2程が流域面積となる。)辺りから津風呂湖へ導水して津風呂湖の水利用 に余裕を持たせて発電に使いた い。[→開発篇]

ただ高見川流域には水発は皆無だったものの昔あった発電所が復活してしまった。。ただ規模は小さく水力開発を邪魔する程の水は使って無さそう。更に上流の 水を使って発電も可能っぽい
[廃止]筑波峯 (つくばね)発電所[wiki]
運開:1914(吉野水力電気(株)1912設立) 廃止:1963(関西電力(株))
出力:45kW
取水:日裏川
放水:日裏川
東吉野水力発電(株) つくばね発電所[東吉野水電] [村観光協会][wiki] [セキュリテ]
運開:2017(2014会社設立)
出力:82kW
使用水量:0.1m3/s
有効落差:105m
水車:クロスフロー※チェコ共和国シンク社製の水車発電機。出力 82kW
取水:日裏川(400m付近か?)
放水:日裏川(EL.284m 付近か?)
>2013年(平成25年)、地元有志者らが村の活性化を目指し、「つくばね発電所」の復活プロジェクトを開始。
>その後、「東吉野村小水力利用推進協議会」と「株式会社CWS(ならコープグループ)」の共同出資により「東吉野水力発電株式会社」を設立。金融 機関からの借入と市民ファンドにより資金を調達し、つくばね発電所を復活させました。



 21.5
21.5


 21.5
21.5





 出典:奈良県
出典:奈良県