社名
|
発電所名
|
所在地
|
最大出力
(MW)
|
各ユニット仕様・詳細
|
その他・備考
|
| No. |
単機容量
[九電受電分]
|
LFC
最低出力
|
最低出力
|
運開
年月 |
発電
効率 |
発電
種別 |
使用
燃料 |
中
電
|
三隅 |
浜田市三隅町岡見
|
2,000
|
1号機
|
1,000
|
|
|
1998.6
|
|
USC
|
石炭
|
2
号機は400MWで計画され着工延期されていた
その後電力不足を機会に1000MW に増強の上建設が決定。 |
| 2号機 |
1000 |
|
|
2022.11予
|
|
|
松江原子力
|
松江市鹿島町
|
(820)
(→2,193)
|
2号機
|
820
|
|
|
1989
|
|
BWR
|
原子力
|
|
| 3号機 |
1373 |
|
|
未定 |
|
ABWR |
電発
|
竹原
|
竹原市忠海
|
600
|
新1号機
|
600
|
|
|
2020.6
|
|
USC
|
石炭・木質バイ(10%)
|
嘗ての中四幹線のお膝元にあるが意外にも九電への供給は無し?
|
合計
|
2700(新設石炭完成後:4300)
|
|
|
| 四電 |
橘湾 |
徳島県
阿南市
橘町 |
700 |
1号機 |
700 |
|
|
2000.6
|
44%[L]
|
USC
|
石炭 |
四電と電発の発電所が隣接している。
関電への
|
| 電発 |
橘
湾火力
|
2100
|
1号機
|
1,050
[47] |
|
368[16]
|
2000.7
|
45%[L]
|
USC
|
石炭 |
| 2号機 |
1,050
[47] |
|
368[16]
|
2000.12
|
45%[L]
|
USC
|
石炭 |
四
電
|
西条
|
愛媛県
西条市喜多川
|
406
→800
|
1号機
|
156
→500
|
|
|
1965.11
→2022予
|
|
USC |
石炭・木質 バイ(2%以下)
|
2022年運開予定で1号機のリプレースを計画
(バイオマスはどうなるのかね?)
|
伊方
|
|
890
|
3号機
|
890
|
|
|
|
|
|
原子力 |
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電
発
|
松島火力
|
長崎県西海市
|
1000
|
1号機
|
500
[187]
|
|
250[91]
|
1981.1
|
42%[L]
|
SC
|
石炭 |
石炭火発で初のSC
|
2号機
|
500
[187]
|
|
250[91]
|
1981.6
|
42%[L]
|
SC
|
石炭 |
九
電
|
松浦
|
松浦市
志佐町
白浜免 |
開発 |
700
(1700予)
|
1号機
|
700
|
280
|
105
|
1989.6
|
40.7
|
SC
|
石炭 |
隣接する電発松浦火力と併せ「東洋一の石炭火
力」と称された。
(九電2号機と併せて計3,700MW,中電碧南火力が4,100MW。)
九電2号機は2001.4には工事が開始されたがその後中断。
運用開始時期が2023年以降に変更となった。
その後計画が早められ2016.1工事再開,2019.6に運転開始した。 |
2号機
|
1,000
|
|
|
2019.6
|
46%[L]
|
USC
|
電発
|
松浦火力
|
瀬崎 |
2,000
|
1号機
|
1,000
[378]
|
|
400[147]
|
1990.6
|
43%[L]
|
SC
|
| 2号機 |
1,000
[377] |
|
350[126]
|
1997.7 |
44%[L]
|
USC
|
九
電
|
苓北 |
熊本県天草郡
苓北町 |
1,400 |
1号機
|
700
|
210
|
105
|
1995.12 |
42.1%[H]
|
SC
|
石炭 |
構内に余熱を利用した海水から食用塩を製造する設備あり>>wiki
|
2号機
|
700
|
210
|
105
|
2003.6
|
42.8%[H]
|
USC |
玄海
|
|
2,360
|
3号機
|
1,180
|
|
|
1994.3
|
|
PWR
|
原子力 |
2018年再稼働
|
4号機
|
1,180
|
|
|
1997.7
|
|
PWR
|
原子力
|
川内
|
|
1,780
|
1号機
|
890
|
|
|
|
|
PWR
|
原子力 |
2015年再稼働
|
2号機
|
890
|
|
|
|
|
PWR
|
原子力
|
九州合計
|
10,240
|
九電石炭計:3,100MW 九電原子力計:4,140MW 九電合計:
7,240MW 電発合計:3,000MW 石炭合計:6,100MW
九州老朽石炭(SC)計:
3,400MW(内 九電合計:1,400MW 電発合計2,000MW)
|
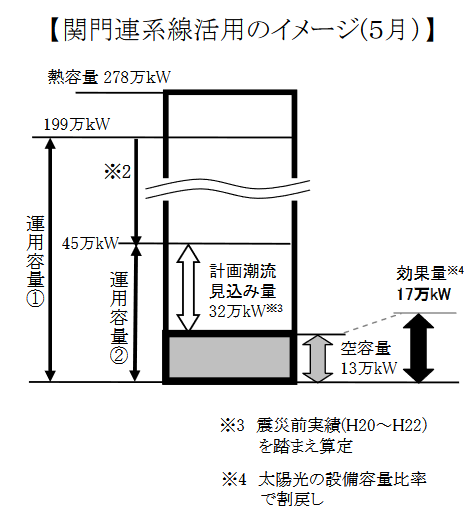
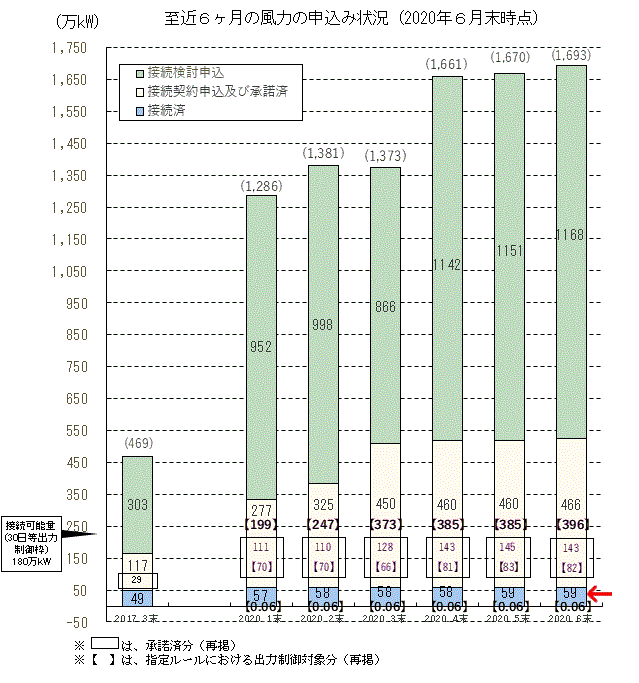 出典:九州配送電
出典:九州配送電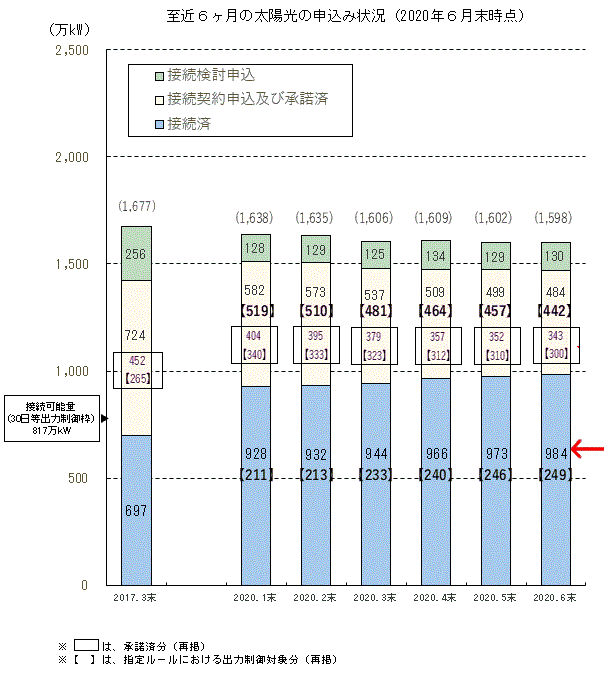 出典:九州配送電
出典:九州配送電